遺留分を請求するには
遺留分とは
遺留分とは、一定範囲の相続人に最低限保障されている遺産の取得割合のことをいいます。
亡くなった人が、遺言で「自分の財産を全て〇〇に相続させる」と書き遺していたとしても、一定の相続人(遺留分権利者)であれば、最低限の遺産を取得することができます。
遺留分を請求できる人
では、遺留分を請求することができる相続人は誰でしょうか。
これは法律で定められており、亡くなった人の相続人のうち、配偶者、子ども(代襲相続人を含む)、直系尊属(親や祖父母)です(民法1042条)。
亡くなった人の兄妹姉妹(及びその代襲相続人)は、遺留分を請求することができないので注意しましょう。
遺留分を請求できる場合とは?
どのような場合に遺留分を請求することができるのでしょうか。
これは、亡くなった人が遺言を遺しており、その遺言の中で遺産を特定の人に多く渡す旨が記載されていて、相続人が自らの最低限の相続分(遺留分)を確保できないような場合です。
例えば、亡くなった父親が離婚後に再婚しており、「遺産を全て後妻に相続させる」という内容の遺言を遺していた場合、前妻の子は、自分の遺留分が侵害されているとして、後妻に侵害された遺留分を請求することができることになります。

誰に遺留分を請求するのか
では、誰に対して遺留分を請求するのでしょうか。
これは、遺留分を侵害する遺贈または贈与を受けた者に請求します。
先ほどの例(後妻に全ての遺産を相続させる遺言を遺した例)でいえば、全財産を相続すると遺言で指定された後妻に対して請求を行うことになります。
相手方になると思われる者が複数いて、請求時点で誰が債務者であるか明確ではないときは、とりあえず請求できると思われる相手方すべてに請求しておくのが無難でしょう。
遺言があるかわからない場合は?
亡くなった人と疎遠になっており、遺言書があるか調査するにはどうすれば良いでしょうか。
侵害がされた遺留分を請求するには

自分の遺留分が侵害されたと分かった場合は、どのようにして請求すれば良いのでしょうか。
これは、遺留分を侵害している人に対して、侵害されている遺留分の請求を行うという意思表示を行う方法でします。
具体的には、遺留分を侵害している人に対して書面で遺留分侵害額請求を行うことを通知します。
このとき裁判や調停で請求する必要はありません。
遺留分の請求は、請求できる期間が決まっているので(1年)、いつ請求したかわかるような方法(内容証明郵便など)で請求しましょう。
請求するときに金額を明示する必要はあるか
遺留分を請求しようと思っても、亡くなった人の遺産総額が分からないのでいくら請求したら良いかわからないという場合もあると思います。
このような場合は、どのように請求すれば良いのでしょうか。
この場合は、具体的に「〇〇円」請求しますと通知しなくてもよく、侵害されている遺留分を請求するということを伝えれば問題ありません。
通知をした後はどうすれば良いか
侵害されている遺留分を請求することを相手に通知した後は、どのようにすれば良いのでしょうか。
もし、亡くなった人と疎遠で相続財産の内容が分からない場合は、請求相手に対して相続財産を開示してもらうよう求めます。
そして、相続財産の全貌を把握することができれば、侵害されている自分の遺留分額を計算して、相手にその侵害額支払いを求めます。

まずは話し合いでの解決を目指す
まずは相手方との間で、支払ってもらう金額について話し合いを求めます。
話し合いがまとまったら、合意書を作って侵害された遺留分額の支払いを求めます。
話し合いでの解決が難しければ調停・裁判も
相手との話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります(調停前置主義・家事事件手続法257条)。
調停でも話がつかずに調停が不成立となった場合は、裁判を起こして解決することになります。
裁判を起こす場合は、家庭裁判所ではなく、被相続人の最後の住所地を管轄する地方裁判所が管轄裁判所になります(民事訴訟法5条14号)。
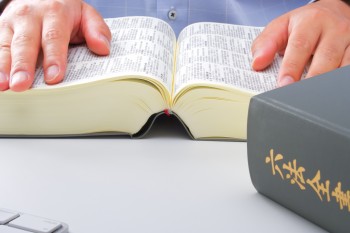
1年以内に請求することが必要
遺留分を請求できる期間は決まっています。
具体的には、「相続の開始(死亡)と遺留分を侵害する贈与等があっ2025たことを知ったときから1年」以内に請求する必要があります。
なお、このとき1年以内に「遺留分を請求する」という意思表示を相手にすれば足ります。
1年以内にお金を取り戻す必要があるという訳ではありません。











