遺留分が侵害されている・遺留分を請求された
遺留分とは
✔ 遺留分は最低保証されている権利
被相続人が、『全財産を誰か一人に相続させる』という遺言を遺していた場合にも、一定の相続人であれば遺留分として最低限の権利を主張することができる場合があります。
このように、被相続人の財産の中で一定の相続人に最低限保証されている権利のことを遺留分といいます。
✔ 遺留分が侵害されている場合は請求ができる
自分の遺留分が侵害されている場合は、侵害されている金額を請求することができます。
遺留分には、残された近親者の生活保障や、共同相続人の公平を図るといった目的があります。
遺留分を請求できるのは誰か
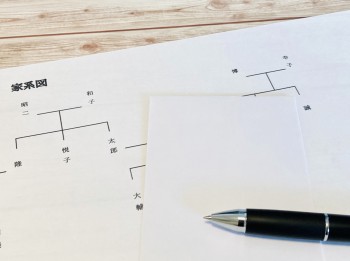
法定相続人であれば誰でも遺留分の権利を有している訳ではありません。遺留分の権利を有する人は、「兄弟姉妹以外の相続人」(民法1042条1項)です。
つまり、遺留分の権利を有するのは、以下の人だけになります。
①被相続人の配偶者
②子
③直系尊属(父母や祖父母など)
兄弟姉妹には遺留分は認められていませんので注意が必要です。
遺留分を請求できるのはいつまでか

遺留分はいつまでも請求できる訳ではありません。
✔ 1年で時効消滅する
遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が、相続の開始と遺留分を侵害する遺贈等があったことを知ったときから1年で時効消滅します(民法1048条前段)。
この1年という期限は長いようにも思えますが、あっという間に過ぎてしまうため注意が必要です。
このため、遺留分の侵害があると分かった時点で、すぐに遺留分を請求するという意思表示をしておくことが必要です。
✔ 請求した後も5年で時効消滅する
1年以内に遺留分を請求する意思表示を行った場合でも、遺留分侵害額請求権は金銭債権であるため、通常の金銭債権と同様に5年で時効により消滅します(2020年4月1日施行の改正民法)。
このため、遺留分を請求する意思表示を行った後、そのまま何もしないまま放っておくと5年で時効消滅する可能性があります。
✔ 死亡から10年経過した場合も消滅する
相続人の死亡や遺留分の侵害があることを知らないまま相続開始(死亡時)から10年を経過した場合も、遺留分侵害額請求権は消滅します(除斥期間、民法1048条後段)
遺留分侵害額を請求するには

✔ 請求することが必要
遺留分の権利を有するからといって、何もしなくても当然に貰える訳ではありません。
遺留分を侵害されている相続人は、遺留分を侵害している人に対し、請求してはじめて財産を取り戻すことができます。
✔ 請求する方法には特に決まりはない
では、遺留分は、どのように請求すれば良いのでしょうか。
遺留分侵害額請求の方式に特に決まりはなく、遺留分を侵害している受遺者又は受贈者に対する意思表示さえあれば効力を生じます。
具体的には、遺言で財産を全部相続すると定められた人に対して、書面などで遺留分を請求する旨を通知するということになります。
このとき、遺留分の請求をしたという証拠を残すため、内容証明郵便などの方法で相手に対して意思表示を行うことが望ましいでしょう。
✔ 遺留分の計算方法は複雑
遺留分侵害額としてどのくらいの金額を請求することができるかについては、計算が複雑であるため弁護士にご相談いただく方が安心です。
遺留分を請求されたら

遺留分を請求された場合は、どうすれば良いのでしょうか。
✔ 支払いに応じるのが原則
遺留分は、民法上認められた権利であるため、正当な権利のある遺留分権利者から遺留分の侵害額請求をされた場合は、支払いに応じなければらないのが原則です。
ただし、相手から請求されていない場合は支払う必要がありませんので、こちらから遺留分侵害額の支払いを申し出る必要はありません。
✔ 遺留分を請求できる人は決まっている
遺留分を請求できる人は法律で決まっているので(配偶者、子、直系尊属のみ)、遺留分の権利がない人からの請求には応じる必要がありません。
✔ 遺留分を請求できる期限も決まっている
遺留分を請求することができる期限も決まっていますので、期限が過ぎている請求については支払いに応じる必要はありません。
被相続人の死亡から1年を経過した後の請求であれば、まずは時効消滅しているかどうかを検討する必要があります。
✔ 遺留分の請求額を検討する
遺留分を請求された場合でも、はっきりとした請求金額が示されておらず、いくら請求されているのか分からない場合があります。
また、明らかに過大であると思われる金額を請求されるような場合もあります。
遺留分侵害額がいくらであるか、いくら支払うのが妥当であるか、金額をよく検討して支払いに応じる必要があります。
解決までの流れ

遺留分を請求したら(請求されたら)、まず当事者間で話し合いを行って解決を目指します。
話し合いで支払額が決まったら、当事者間で合意書などの書面を作成し、合意した金額の支払いをして終了となります。
話し合いでの解決が難しい場合は、調停や訴訟で解決することを目指すことになります。
遺留分についての紛争は調停前置主義を取られており、まずは調停を申し立てて解決を目指すことが原則となっています。
もっとも、遺留分についての紛争は、調停で解決することが難しいことも多いため、調停を経ずに最初から訴訟を提起しても、そのまま裁判が進められるという運用がなされることも少なくありません。
✔ 遺言書で一部の相続人に圧倒的に有利な内容になっている
✔ 遺留分を取り戻したい
✔ 遺留分を請求された
このような場合は、是非一度、法律事務所瀬合パートナーズにご相談ください。
関連記事










