遺産分割問題でお困りの方へ
遺産分割の問題は誰にでも起こります
遺産分割の問題は、資産家のご家庭に限らず、ごく普通のご家庭にも起こります。
仲が良かった兄弟間、親子間でも、遺産分割をめぐって争いが起きているのが現実です。
話し合いで円満に解決することができれば良いですが、話し合いでの解決が難しいケースも存在します。
そのような場合は、家庭裁判所で調停や審判をしなければならない場合もあります。
弁護士に相談した方が良いケースとは
では、どのような場合に弁護士に相談するのが良いのでしょうか。
以下のような場合はご相談をおすすめします。
✔ 協議で自分だけ不利な内容になっている
✔ 相続人の一部が話し合いに応じない
✔ 相続人が遺産を開示してくれない
✔ 遺産の評価に争いがある
✔ 相続財産を使いこんだ相続人がいる
✔ 多額の生前贈与を受けた相続人がいる
✔ 相続人が多すぎて話ができない
✔ 相続人と連絡が取れない
✔ 相続人同士の仲が悪い、疎遠である
✔ 相続人の中に認知症の人がいる
✔ 遺留分を請求したい、請求された
✔ 弁護士から遺産分割協議書が届いた
✔ 遺産分割調停が申し立てられた
✔ 二代、三代前の相続が未了である

調停・審判を行う必要がある場合とは
遺産分割の話し合いが難しい場合は、調停や審判を行って解決を目指すことになります。
調停や審判は、裁判所が関与するため裁判と同じようなイメージを持たれるかもしれません。
しかし、調停は、調停委員を介して相続人間で話し合いを進めていく手続です。
調停委員が相続人の間に入って話を仲介してくれるため、冷静な話し合いを進めることができ、相続問題解決に有効な手続となります。
具体的に、以下のような場合には、調停を利用して解決することを検討します。

✔ 相続人の一部が話し合いに応じない
相続人の一部が遺産分割の話し合いに応じない場合は、調停を申立てて話し合いを行うのが良いでしょう。
話し合いには応じなくても、調停には出席するという相続人も珍しくありません。
また調停を申立てたものの、その相続人が調停にも出席しない場合は、家庭裁判所の審判により遺産分割が可能となります。
✔ 相続人と連絡が取れない・行方不明である
相続人の一部が海外に行って連絡が取れなくなっている、居場所がわからず行方不明となっているというような場合も、遺産分割調停を申し立てることを検討します。
この場合も、調停を申立てても連絡がつかない場合は、家庭裁判所の審判により遺産分割を行うことになります。
✔ 相続人が多数いる
相続人が10名以上いる場合など、相続人が多数いる場合も遺産分割調停を申し立てることを検討します。
相続人が多数いると、全員と話し合いの場を持つことは困難であることが多いです。
また、相続人全員の意見を話し合いでまとめるということが難しくなる傾向にあります。
このため相続人が多数いる場合も、遺産分割調停の申し立てを検討し、調停で話し合いがまとまらなければ、審判により遺産分割を行います。
✔ 相続人間で意見の対立が大きい場合
相続人間で、遺産分割についての意見の対立が大きい場合も、遺産分割調停の申し立てを検討します。
例えば、相続人の一人が過去に被相続人から大きな金額の生前贈与を受けているため、特別受益があることを主張したいが、その相続人が特別受益を認めない場合などが考えられます。
また、不動産など遺産の評価額について当事者間で大きな意見の対立がある場合は、最終的には家庭裁判所で鑑定を行って評価を決めなければ決着がつかないケースもあります。
解決までの流れ
遺産分割の一般的な流れは、簡単にまとめると次のようになります。
✔ 相続人と相続財産を確定する
✔ 相続人全員で遺産分割協議を行う
✔ 協議ができなければ調停を行う
✔ 調停が不成立になった場合は審判で決めてもらう
✔ 具体的な相続手続を行う
✔ 相続人と相続財産を確定する
まずは被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せ、法定相続人を確定します。
また、その法定相続人の相続分がいくらであるかということも確認します。
もし被相続人が遺言を遺していれば、遺言に従って相続するため、遺言の有無も確認しておきます。
また、被相続人の遺産(例えば、預金、不動産、株式、自動車、その他)の内容と金額を調査して確定しておきます。
✔ 遺産分割協議を行う
相続人と相続財産が確定したら、相続人間で遺産分割についての協議を行います。すなわち、どの遺産を誰がいくら取得するかということを決めていきます。
相続人が一人でも欠けているとその遺産分割協議は無効となってしまいますので、必ず相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
遺産分割協議がまとまったら遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には、どの財産を誰が取得するのかということを明確に記載し、相続人全員がそれに署名押印して完成させます。遺産分割協議書には実印で押印して、印鑑証明書を添付します。

✔ 遺産分割調停を行う
遺産分割協議をした結果、話し合いがまとまらない場合は、遺産分割調停を申し立てて解決を目指します。
調停は、家庭裁判所の調停委員が話を仲介してくれますが、基本的には当事者の話し合いによって合意を目指します。
調停において遺産分割の話し合いがまとまれば、家庭裁判所が調停調書を作成して遺産分割が成立することになります。
✔ 審判で決めてもらう
何らかの理由で、遺産分割調停が成立しなかった場合は、家庭裁判所の審判により遺産分割の内容が決まります。
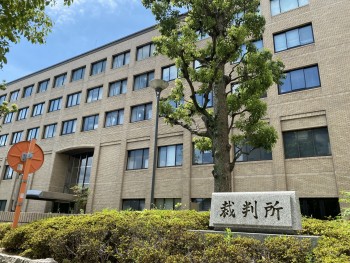
✔ 具体的な相続手続を行う
遺産分割の問題が決着して、遺産分割協議書、調停調書、審判ができれば、それをもって具体的な相続手続を行います。
例えば、預金の名義変更や解約、不動産の名義変更、株式などの名義変更手続です。
この具体的な相続手続を完了すれば、遺産分割はすべて終了となります。











