特別受益を主張するには
相続人の一人が被相続人から生前贈与を受けており、それが特別受益に当たる場合、どのようにすればよいのでしょうか。
特別受益については、遺産分割協議において相続人の一人から特別受益があることの指摘があって初めて検討することになります。
相続人の誰からも特別受益の指摘が無い場合は、これを検討する必要はありません。
相続人全員の意向を確認する
相続人の一人から特別受益の主張があった場合、まずは相続人全員の意向を確認します。
相続人の間で、相続人の一人が特別受益を受けたこととその特別受益の金額について合意ができれば、それを基準にして各人の相続分を計算します。
特別受益があったこと(生前贈与等)についての証拠があれば、当事者間での合意がスムーズに進む可能性があります。証拠があればそれを相続人に提示するようにしましょう。
特別受益を主張する人
特別受益を受けた人以外の相続人が、その特別受益があったことを主張します。
特別受益を主張する場合は、①贈与があったこと(いつ、何を、いくら)、②その贈与が生計の資本等としてなされたものであったことを主張します。
これに対して、特別受益を受けたと指摘された相続人は、上記①②がなかったことや、「持ち戻し免除の意思表示」があったことなどを主張することになります。
特別受益があったことの証明
特別受益があったと主張する者が、それについての証拠を提出してそれを証明することが必要です。
これに対し、特別受益を受けた者が「持ち戻し免除の意思表示」があったと主張する場合は、「持ち戻し免除の意思表示」があったと主張する者が証拠を提出して証明しなければなりません。
特別受益の証拠について

金銭の贈与があった場合
被相続人から相続人に金銭が贈与された場合、被相続人の預金口座から金銭が移されたことを証明する必要があります。
このため、まずは被相続人名義の預金口座の通帳を確認したり、金融機関から過去の取引履歴を取り寄せてお金の動きを確認します。
被相続人の預金口座から、相続人の預金口座に振込みで金銭が贈与された場合は、それ自体が非常にわかりやすい証拠となります。
一方、被相続人の預金口座からまとまった金額の現金が出金されているものの、それが手渡しで相続人の一人に渡された場合は証明が難しくなります。
その出金があったときと近接する日時で、例えば「長男に〇〇万円を渡す」等と記載された日記やメモが残っている、金銭の授受があったことがうかがえるメールや手紙のやり取りがあったことを示す資料などが必要となります。

不動産の贈与があった場合
不動産の贈与があった場合は、比較的証明することは簡単です。
不動産が贈与された場合、贈与を原因とする登記名義の変更が行われているはずです。
法務局で不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得すれば、被相続人から相続人に贈与されたことが分かります。
その登記事項証明書が、特別受益の証拠となります。
もし、不動産自体を贈与したのではなく、不動産購入のための資金援助をしていた場合は、上記1と同様に、購入時期の預金口座の取引履歴が重要な証拠になります。
相続人が不動産を購入した時期に、被相続人の口座から多額の現金が出金されているような事実があれば、それについての取引履歴を提出することになります。
生活費を負担してもらっていた場合
被相続人が相続人の生活費を負担していた場合も、被相続人名義口座の取引履歴が証拠となります。
他にも、被相続人名義のクレジットカードで相続人の生活費の支払いがなされていた場合は、クレジットカードの利用明細が証拠となるでしょう。
もっとも、相続人が被相続人と同居していた場合や生活費負担額が少額な場合は、特別受益として認められない場合もあります。

自動車の贈与があった場合
自動車が贈与されたことの証拠としては、自動車の登録事項等証明書や贈与契約書が挙げられます。
自動車の登録事項等証明書には、移転登録の時期や前の所有者の氏名等が記載されています。
このため、被相続人の生前に被相続人から相続人へ移転登録されていた場合等には、登録事項証明書は重要な証拠となります。
持ち戻し免除の意思表示の証拠について
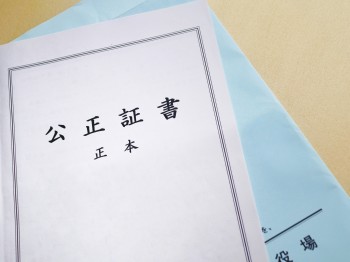
遺言などがある場合
特別受益を受けた相続人が、「持ち戻し免除の意思表示」があったことを証明するにはどうすれば良いのでしょうか。
被相続人の遺言(公正証書遺言など)で、持ち戻し免除の意思表示が記載されていることがあるので、それがあればその遺言書を証拠として提出します。
黙示の意思表示
また、持ち戻し免除の意思表示が明示的になされていなくても、黙示的な意思表示があったものと判断される場合もあります。
黙示の意思表示かあったかについては、贈与の内容やその価額、贈与がなされた動機、被相続人と受贈者との生活関係、被相続人と相続人の職業・経済状態・健康状態、他の相続人が受けた贈与の内容・価額・持ち戻し免除の意思の有無等を考慮して判断されることになります。
例えば、以下のような場合は、黙示の持ち戻し免除の意思表示があったと考えられる場合があります。
✔ 家業を継がせるために特定の相続人に特定の財産を相続させる必要がある場合
✔ 病気などで生活することが困難な相続人に対して生活保障のために贈与がされた場合
✔ 妻の老後を支えるために金銭の贈与がなされた場合
✔ 相続人全員に相応に贈与がなされているような場合
このような場合は、上記事情についての具体的事情について主張し、その証拠を提出することになります。

婚姻期間が20年以上の夫婦間の居住用不動産の贈与について
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、一方から他方に対して居住用建物やその敷地について贈与がなされた場合は、持ち戻し免除の意思表示があったと推定される民法の規定があります(民法903条4項)。
このため、この要件に該当する場合は、婚姻期間の証明と居住用建物の贈与があったことを証明すれば良いことになります。
関連記事











