遠方にいる相続人との遺産分割
遠方にいる相続人とどのように話し合うか
相続人が遠方に住んでいたり、各地に散らばっている場合でも、遺産分割協議をすることはできます。
遺産分割協議をする場合、相続人全員が集まって話し合いをする必要はありません。
協議方式についての決まりはなく、電話やメール、手紙などで連絡を取り合って、相続人全員が同じ内容での遺産分割方法を合意すれば、遺産分割協議は成立します。
遺産分割協議書の作成方法
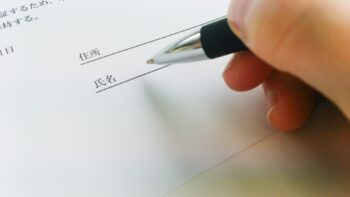
相続人間で遺産分割協議がまとまった場合、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書を作成する場合も、相続人全員が集まって署名押印する必要はなく、郵送でやりとりして作成することが可能です。具体的には、以下のような方法により行います。
✔ 持ち回り方式
遺産分割協議書を1通作成し、相続人全員に順番に回して、相続人全員に署名押印をしてもらう方法です。
具体的には、相続人Aが署名押印し、その後B→C→Dと全員が署名押印するまで順番に郵送で回していく方法です。
この方法は、1通の遺産分割協議書に相続人全員が連署する形になるので、一番わかりやすい協議書の形式かもしれません。
しかし、例えば、Aさんが署名押印した後、Bさんに郵送し、Bさんが署名押印した後、Cさんに郵送し・・・という流れになるため、完成までに時間がかかります。また誰かが紛失してしまうと最初からやり直さなければなりません。
相続人が2~3名程度であれば、この持ち回り方式で対応することができますが、相続人が多数いるような場合には、現実な方法とはいえません。
✔ 遺産分割協議証明書
もう一つの方法として、遺産分割協議証明書による方法があります。
これは、遺産分割協議証明書という同じ内容の書類を相続人の人数分作成し、相続人それぞれに郵送して署名押印をしてもらう方法です。
この場合、例えば、同じ内容の遺産分割協議証明書を作成し、相続人A、B、C、Dに一斉に郵送し、各自署名押印したものをそれぞれ返送してもらえばよいので、時間や手間を大幅に短縮することができます。
相続人全員分の遺産分割協議証明書がそろえば、遺産分割協議書と同等の効力を有することになりますので、相続登記手続や預金の払い戻し手続をすることが可能です。
なお、持ち回り方式による場合でも、遺産分割協議証明書による場合でも、相続登記や預金の払い戻し手続をする場合は、相続人が署名して、実印により押印をした書面に、相続人全員の印鑑登録証明書を添付する必要があります。
このため遺産分割協議書や証明書を郵送してもらうときには、印鑑登録証明書も添付して送ってもらうようにしましょう。
調停・審判

✔ 管轄裁判所
相続人同士で遺産分割の方法がまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。
相続人が遠方にいる場合、どこの裁判所に調停を申し立てるかというと、「相手方の住所地を管轄する家庭裁判所」になります。
このため、遠方に住んでいる相続人との間で遺産分割調停を行う場合、相手の住所地である、遠方の家庭裁判所に申立てを行うことになります。
このとき、相手方となる相続人が複数おり、それぞれ住所地が異なる場合は、いずれかの住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てることができます。
例えば、相手方となる相続人Aが北海道、Bが沖縄、Cが大阪に住所がある場合、大阪の家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
また、相続人のうち自分だけが遠隔地に住んでいて、他の相続人全員が遠方に住んでいる場合、遠方の家庭裁判所で調停を行わなければならない場合もあります。
その場合、電話会議システムやWEB会議システムなどを利用して出席することができる場合があります。詳しくは管轄裁判所で方法をご相談ください。
また、弁護士に依頼すれば、代わりに家庭裁判所に出席してもらうことも可能です。
✔ 調停に代わる審判
相続人が遠方に住んでいて、遺産分割調停に出席しない相続人がいる場合、家庭裁判所が、調停に代わる審判(家事審判法284条1項)をする場合があります。
調停に代わる審判は、調停が成立しない場合に、家庭裁判所が、当事者の衡平に考慮し、一切の事情を考慮して、遺産分割方法を決める手続です。
この調停に代わる審判に不服がある場合は、2週間以内に異議申立てを行います。適法異議申し立てがあれば、調停に代わる審判は確定せず、通常の審判手続に移行します。
調停に出席しない相続人は、調停には協力的ではないものの、他の相続人の合意案には特に反対もしないということも多いです。
このため、家庭裁判所が、これまでの調停での話し合い(欠席した当事者を除く話し合い)を踏まえ、欠席当事者にも不利にならないように配慮した内容の調停に代わる審判を出すことで、決着がつく場合が少なくありません。










