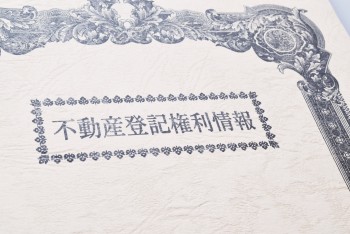土地と建物の名義が違う場合の相続問題
第1 はじめに
土地と建物の名義が異なることは、相続に限らず日常的に見られますが、相続が発生すると、複雑な法的問題が発生する場合があります。
そこで、本記事では、相続時に土地と建物の名義が異なる代表的なケースを紹介し、各ケースにおける適切な対処法を解説していきます。
第2 土地と建物の名義が異なる場合
土地と建物の名義が異なることは相続の場合に限りませんが、相続の場合で多いのは、例えば、次のような状況で父の相続が発生した場合です。
①父が所有する土地に息子が家を建てた。
②父が所有する土地に父と息子が共有名義の家を建てた。
③すでに他界した祖父が所有していた土地に父が家を建てたが、土地の名義が祖父のままになっていた。
④父が土地を賃貸しており、賃借人が賃借人名義の家を建てて居住している。
⑤父が土地を借りており、父が父名義の家を建てて居住している。
| 名義(土地) | 名義(建物) | |
| ① | 父 | 長男 |
| ② | 父 | 父+長男 |
| ③ | (祖父)※既に死亡 | 父 |
| ④ | 父 | 借主(第三者) |
| ➄ | 貸主(第三者) | 父 |
第3 ケース別の対処法
①と②の場合(土地が父名義、建物が長男名義もしくは共有名義)
この場合、①であれば土地、②であれば土地と建物(父の共有持分のみ)が相続財産となります。
いずれのケースでも、長男がそのまま建物に居住し続けることが多いと思われます。そのため、土地や建物(父の共有持分)は、長男が単独で相続するのが一般的でしょう。
ただ、長男がこれらを単独で相続したことにより、長男の取得する相続分が他の相続人よりも多くなる場合には、他の相続人との間で金銭的な調整を図る必要があります。
当該不動産以外に相続財産(預貯金、株式等)がある場合には、これらを使って調整できますが、当該不動産以外に相続財産がない場合には、長男が自身の財布から代償金を支払う必要がでてくるため、その原資を用意しておく必要があります。
③の場合(土地がすでに死亡した祖父名義、建物が父名義)
このケースでは、祖父が死亡した際に、祖父の遺産分割が行われていたか否かによって、その後に取るべき手段が変わってきます。
祖父の遺産分割が既に行われていて、父が土地を相続すると決まっていた場合
この場合、単に登記がされていないだけで、父が土地を所有していたことに変わりはありません。そのため、土地・建物ともに父の相続財産となり、父の遺産分割さえまとまれば、あとは実体に沿って相続登記を行うだけで足ります。
今回のケースであれば、祖父の遺産分割協議のときに遡って父名義の相続登記をし、次に、父から土地(と建物)を相続した相続人が父から相続した旨の相続登記をすることになるでしょう。
これで土地と建物は同じ名義に整理されることになります。
祖父の遺産分割がいまだ行われていない場合
この場合、祖父の遺産分割が行われていない以上、祖父の相続人全員で土地を共有している状態となり、父はその共有者のうちの1人にすぎません。
そのため、土地については父が有していた共有持分のみが父の相続財産となり、父の遺産分割を行っても、土地の共有状態を完全に解消することはできません。この状態を放置すると、父以外の共有者にも相続が発生し、権利関係がどんどん複雑になってしまいます。
そこで、父から土地の共有持分を相続した相続人は、その他の共有者を調査した上で、当該共有者から共有持分を買い取って、単独名義にしておくのが望ましいでしょう。
なお、令和6年4月1日から相続登記が義務化され、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されるおそれがあります。これは、過去(=令和6年3月31日以前)に発生した相続に関しても適用されるため(基本的には令和9年4月1日まで)、決して放置しないよう注意しましょう。
④の場合(土地が父名義、建物が第三者名義)
この場合、相続財産は土地ということになりますが、この土地を相続した相続人は、土地の所有権とともに、土地の賃貸人としての地位も父から引き継ぐことになります。そこで、土地を相続した相続人としては、賃借人に対し、今後は自身に賃料を支払うよう連絡することになります。
このように、相続が発生したからといって、賃貸借契約が自動的に終了するわけではないため、注意しましょう。
なお、相続した土地を売却することも可能ですが、第三者が建物を建てて使用している土地であるため、自由度が少ないとして価値は低くなりやすいため、ご注意ください。
⑤の場合(土地が第三者名義、建物が父名義)
この場合、建物のみならず借地権も相続財産となります。
④と同様、父と地主との間で締結されていた賃貸借契約が相続人にもそのまま受け継がれるため、建物を相続した相続人は、地主の許可なく建物に住み続けることが可能です。
反対に、借地権付きの建物を売却しようとする場合には、地主の承諾を得る必要があります。
もし、建物を相続したが活用する予定がないという場合には、建物を買い取ってもらうよう地主に交渉してみるのがよいでしょう。
第4 終わりに
以上のように、土地と建物の名義が異なる場合、相続手続が複雑になりやすいといえます。
また、それぞれのケースごとに適切な対処法が異なるため、なかなか1人で対応するのも難しいと思われます。
そこで、土地と建物の名義が異なる不動産が相続財産となっており、どのように対処すればよいか分からないとお悩みの方は、法律事務所瀬合パートナーズに是非ご相談ください。
関連記事
・不動産の相続について
・不動産の評価方法について
・共有名義の不動産の相続トラブル