遺産分割調停の呼出しを受けたが無視して問題はないか
遺産分割について相続人間の話合いによって解決できない場合、遺産分割調停が申し立てられることがあります。
遺産分割調停が申し立てられた後、家庭裁判所から調停の呼び出しを受けたにもかかわらず、無視しても問題はないのでしょうか。
以下では、遺産分割調停に出席しない場合の具体的なリスクやその対応策について解説します。
遺産分割調停とは
遺産分割調停とは、相続人間で、遺産分割の協議が調わない場合に、家庭裁判所において話し合いを行って解決を目指す法的手続です(民法907条2項)。
遺産分割調停では、相続人間で直接話し合いをすることなく、調停委員会(裁判官1名、調停委員2名)を介して話し合いを進めることができます。
調停期日は1ヶ月に1回程度の頻度で行われます。遺産分割調停が成立するまで1年以上かかることも珍しくありません。
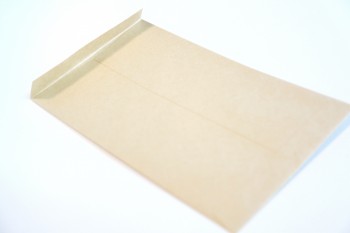
遺産分割調停の呼び出しを受けたら
家庭裁判所は、調停期日に当事者を呼び出すことができ、呼出しを受けた当事者は、調停期日に出頭しなければならないとされています(家事事件手続法258条1項、51条2項)。
家事事件手続法51条3項は、当事者が「正当な理由なく出頭しないときは、家庭裁判所は、五万円以下の過料に処する」と定めています。このため、特に理由がない限りは、調停には出席することが望ましいです。
もっとも、過料に処せられるケースはごく少数であり、呼び出しに応じるか否かは事実上任意であるといえます。

呼出しを無視したらどうなるか
遺産分割調停に複数回欠席すると、当事者間で合意が成立する見込みがないものとして、調停が不成立となることがあります(家事事件手続法272条1項)。
調停が不成立となった場合、遺産分割調停は審判手続に移行し(同条4項)、家庭裁判所が審判を出して遺産分割の方法を決定します。
このとき、例えば、調停に出席して自分の意見を述べていた相続人がいた場合、その相続人の意見や希望が審判の結果に反映されてしまう場合があります。
調停の呼出しを無視すると、遺産分割についての自分の意向を家庭裁判所に伝えることができませんので、自身の希望に沿わない審判結果となる可能性が高くなります。この点で、調停の呼び出しを無視することには大きなリスクがあると言えます。

調停に出席できない場合は
✔ 弁護士に依頼する
調停を無視するつもりはないけれど、調停に出席できそうにない場合はどうすれば良いのでしょうか。
この場合、弁護士に遺産分割調停を依頼するという方法があります。
弁護士は本人に代わって調停に出席することができますので、自身が出席できなくても調停を進めることができます。
また、弁護士に依頼すると調停に出席する時間や心理的負担が軽減する他、遺産分割調停を有利に進めることができる可能性があります。
✔ 期日を変更してもらう
呼び出された日に、体調不良、入院、仕事、冠婚葬祭、海外出張などの理由があってどうしても出席できない場合は、その日は調停を欠席するか、調停期日を変更をしてもらう方法もあります。
その場合は、家庭裁判所に事前に連絡をして当日出席できない旨を伝えます。
もし、家庭裁判所の事情で、調停期日を変更してもらうことが難しければ、その日は欠席するけれども次回以降は出席することを伝えます。
呼出状に家庭裁判所の連絡先が記載されていますのでそこに連絡し、事件番号と当事者である自分の名前を伝えて連絡します。
調停に出席できない場合はご相談ください
以上のとおり、遺産分割調停の呼び出しを無視することは、自身の希望しない審判結果となってしまう可能性や、過料に処せられる可能性があるなどのリスクが伴うため、無視するのはお勧めできません。
遺産分割調停にどうしても出席できな場合や出席したくない事情がある場合は、無視するのではなく適切な対応をすることが必要です。
遺産分割調停の呼び出しを受けたけれども出席しない・できない場合は、まずは一度弁護士にご相談ください。
関連記事
・家庭裁判所での遺産分割調停の進め方
・遺産分割調停はどこの裁判所で行われるのか










